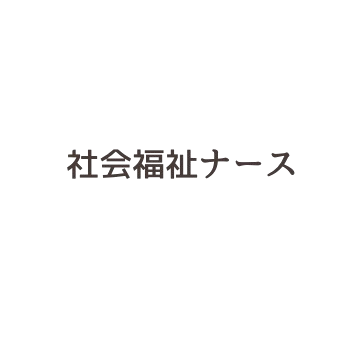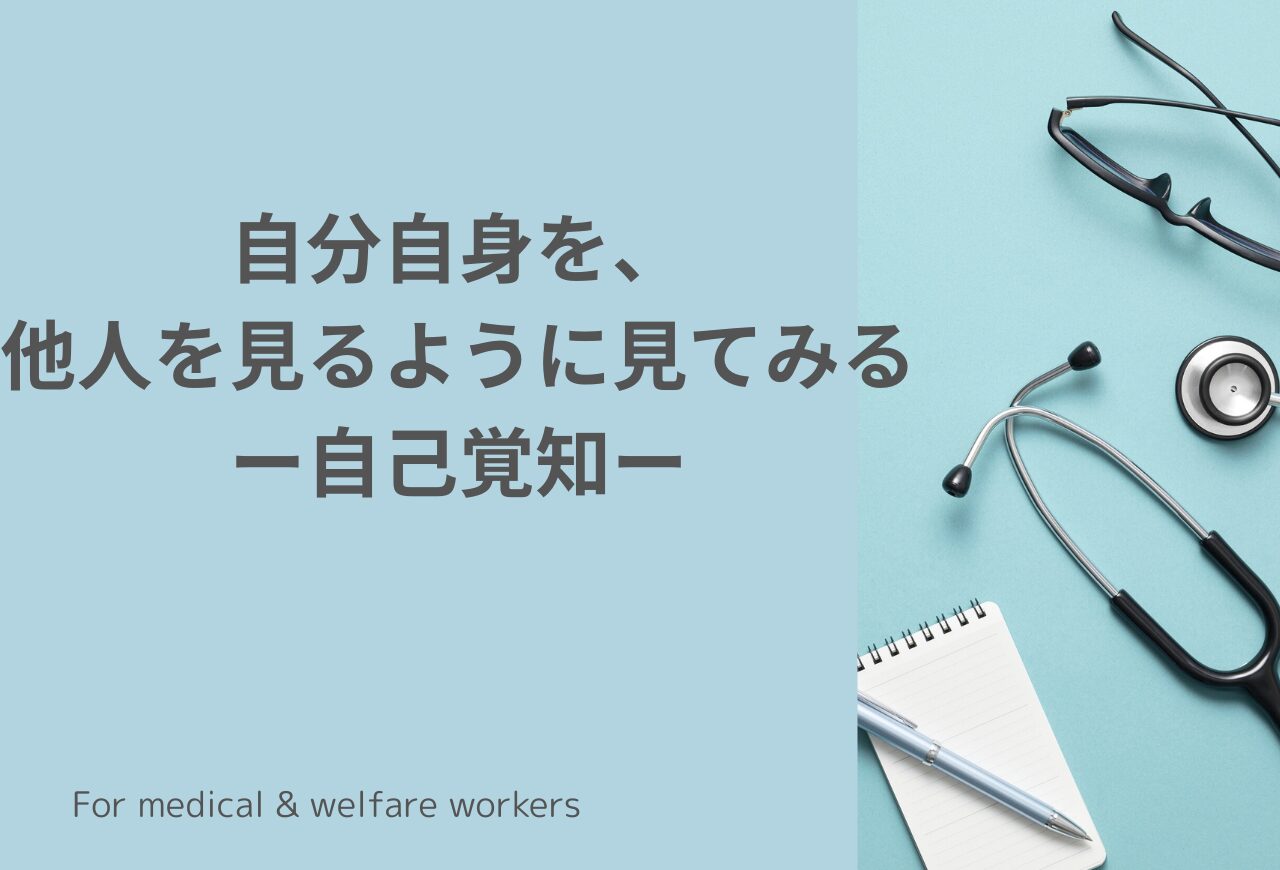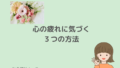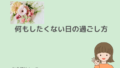自己覚知、という言葉をご存知でしょうか?なんだか難しそうな言葉です。私はこの言葉を、社会福祉士の学習の際に学びました。そして、社会福祉士などソーシャルワークの分野で働く人だけでなく、看護師であっても、他者(クライアント)を客観的に見る必要のある職業、そして対人関係を基本とした職業にとっては、このことはとても大切であることを知りました。一体どんなことなのか、お話ししていきます。
自己覚知とは
一言で言うと、自分を理解すること、です。しかも、感情レベルも含めた、深い自己理解といえます。クライアントに対しての理解を深めるのと同様に、自分に対しての理解を深めるのです。そうすることで、自分では気づかなかった考え方の偏りや癖に気づくことができます。それは一概に悪いことだとは言いませんが、人を相手にする職業である以上、相手にどのように感じられるか、また相手との齟齬の原因に気づくきっかけになります。
今回は、自己覚知のための一つのワークを紹介します。
ワーク 私は〇〇
①私は…から始まる文章を思いつく限りあげてみてください。「私は看護師」といった単語でもいいですし、「私は以前病院で働いていた」「私は海外旅行に行きたい」など、時制もやりたいことでも、自分の身体的特徴でもなんでもよいです。30個ほどでも、それ以上でもできるだけたくさんあげてみてください。そしてこれは誰かに見せないようにしてください。
②書いたものを次のように分類してみます。
誰にでも言えて、知られても大丈夫なことには〇
できれば言いたくない、普段は人に隠していること×
人によっては言える、相手を選んで話すこと△
③書いたものを特徴ごとに分けて、何個当てはまったか数えてみます。
外面的、表面的なもの 個
心理的な特徴 個
客観的事実 個
肯定的な感情が含まれているもの 個
否定的な感情が含まれているもの 個
両方の感情が含まれているもの 個
ワークのまとめ
実際ワークをしてみてどうでしたか?表面的なものや客観的なものはスムーズに書けますが、いくら誰にも見せないといっても、内面的なものや誰にも言いたくないことは書くのに抵抗が働くことが多いようです。私もそうでした。
そして、客観的なものを多く書いた場合は特に、内面的なものを見せることに防衛的になりがちと言えます。この抵抗は自分の心を守るための防衛反応で、自然なことです。自分が「出会いたくない自分」が一体どんな特徴なのか、なぜ出会うことに抵抗感を感じるのかは、考えてみることが大切です。
また、否定的な感情が多い人は自己評価が低い、肯定的な感情が多い人は自己評価が高い、などと自己分析できます。
このワークを対人援助、対人関係においてどう生かすのか
さて、人と関わる職業の場合、クライアントと親しくなりながらも、客観的に観察することが必要です。
その際、自分の考え方が全てでないことを念頭に置く必要があります。例えば、クライアントの気持ちがよくわからない場合などに、自分は自己評価が低い方だけど、このクライアントは自己評価が高い傾向なのかな?など、自分だけのフィルターを通して分析することを防ぐことができます。
また、「出会いたくない自分」がいるように、クライアントにも話したくないことはありますし、またクライアント自身が気づいていない隠れた性質もあります。そしてそれをクライアントは必要に応じて、開示していかなければなりません。その心の防衛的な反応、重たい気持ちが、このワークを通して理解できたのではと思います。話しやすい環境の提供、クライアントに関心を持つ、寄り添って味方になることの大切さがここにあるのです。
またこれは、なにも仕事に限ったことではありません。職種限らず、誰でも人間は人と関わって生きていっています。自分の知りたくない性質は、実は周りの人に知られている部分なのかもしれませんし、どこか近寄りがたいと思われているのかもしれません。性格を治すためのワークではありませんが、自分について知り、周りの人との付き合い方を考える上でも、役にたつ材料になるでしょう。