ストレスや不安に直面したとき、人は無意識のうちに心を守るための防衛機制を使います。その一つが「退行(regression)」です。
退行とは?
退行とは、強いストレスにさらされたときに、心の発達段階を一時的に逆戻りしてしまう心理的な反応です。大人であっても、子どものような振る舞いや感情の出し方をしてしまうことがあります。
「わがままを言う」「泣いて助けを求める」「拗ねる」といった行動は、退行の典型的な例です。
身近な事例
家庭での例
普段はしっかり者の社会人が、実家に帰ると子どものように親に甘えてしまう。適度に甘えることは大切です。ほっと一息つける場があるのは、いいことですよね。
職場での例
強いプレッシャーを受けた社員が、上司に「自分には無理です」「できません」と子どものようにふてくされて拒否してしまう。
以上のように、退行は、実家に帰った社会人のように、癒しとして必要な場合もある一方で、特に強いストレスを感じている場合には苦しみ悲しみが、感情や行動として外に現れ、周囲に影響を与えかねないことも多いです。今回、医療福祉の現場における退行では、主に後者の、ややネガティブな例のほうが挙げられるでしょう。
看護師の現場で見られる退行の事例
患者対応にて
入院患者さんが不安や恐怖を感じると、普段は自立している人でも
「ナースコールを頻繁に押して甘える」 「突然泣き出して助けを求める」「 わがままな要求を繰り返す」 といった行動をとることがあります。これは、病気や入院という強いストレスによって退行が起きているのです。
看護師自身のケースにおいて
忙しい勤務や予期せぬトラブルが重なったときに、
「もう無理!私にはできない!」と感情的になる 普段なら冷静に対処できる場面で、泣いてしまう といった行動をとることがあります。これは責任感の強い看護師でも起こり得る自然な防衛反応です。
看護師同士の人間関係のケースにおいて
職場の人間関係にストレスを感じたときに、
後輩が注意を受けて「どうせ私なんてダメなんです」と拗ねてしまう ベテラン看護師でも、強いストレス下では感情的にふてくされる態度をとる など、子どものような反応をしてしまうことがあります。 この場合、相手を責めるよりも「退行は防衛機制である」と理解して対応することが、健全なチームワークにつながります。
退行のメリットとデメリット(医療職の視点)
メリット
感情を解放できる 泣いたり甘えたりすることで心の緊張が解け、心理的な回復につながる場合があります。 ケアを受けるきっかけになる 患者が退行することで、看護師が不安を把握し、より適切なサポートを行えることがあります。
デメリット
ケアの難しさが増す
患者が退行した状態だと、治療への協力や自己管理が難しくなり、医療者に大きな負担となることがあります。 その都度、スタッフの間で情報共有をし、その患者が真に求めているニーズに気づくことができるかが要になってくるでしょう。
看護師自身の退行は職場に影響する
業務の中で感情的になりすぎると、チームワークに支障をきたしたり、信頼関係に影響を及ぼす可能性があります。 普段と違う、感情的になりすぎている同僚がいる場合は、ちょっと気にしてあげる、また自分が感情的になっているときは一旦冷静になれる方法を日頃から探すことも必要かもしれません。辛いときに話を聞いてくれる信頼できる相手を日頃から作っていると、解決の時間も短くて済むでしょう。
同僚間の誤解を招く
拗ねたり感情的になったりすると「協力的でない」と誤解されやすく、チームの雰囲気を悪化させることがあります。医療現場における退行とは、悪く言ってしまえば、いわゆる、「思い込みによるストレス」であり、そのストレスがさらに新たな思い込みを引き起こしかねず、負のループになりかねません。同僚間での理解も必要になる部分です。
まとめ
退行などの防衛機制は、どの記事でも言っているとおり、「心を守るための自然な働き」であり、大人にも起こることです。自身が、「退行しているな」と気づければいいのですが、これに関しては他の防衛機制と比べても、自分では気づきにくいものではないかと感じます。人は苦しい、悲しいと感じているときほど冷静にはなりにくく、またその苦しみ、悲しみに向き合う必要があるからです。
医療現場では患者さんだけでなく、看護師自身や同僚にも見られるため、「退行が出ているのは弱さではなく、心が助けを求めているサイン」と捉えることが大切です。理解と共感をもって対応することで、信頼関係やチーム医療の質を高めることにつながります。
他の防衛機制について
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~
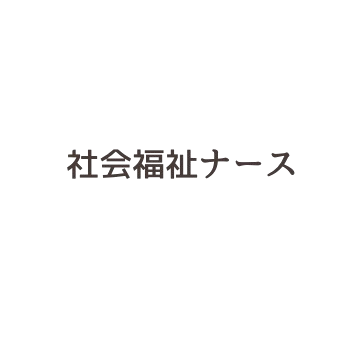
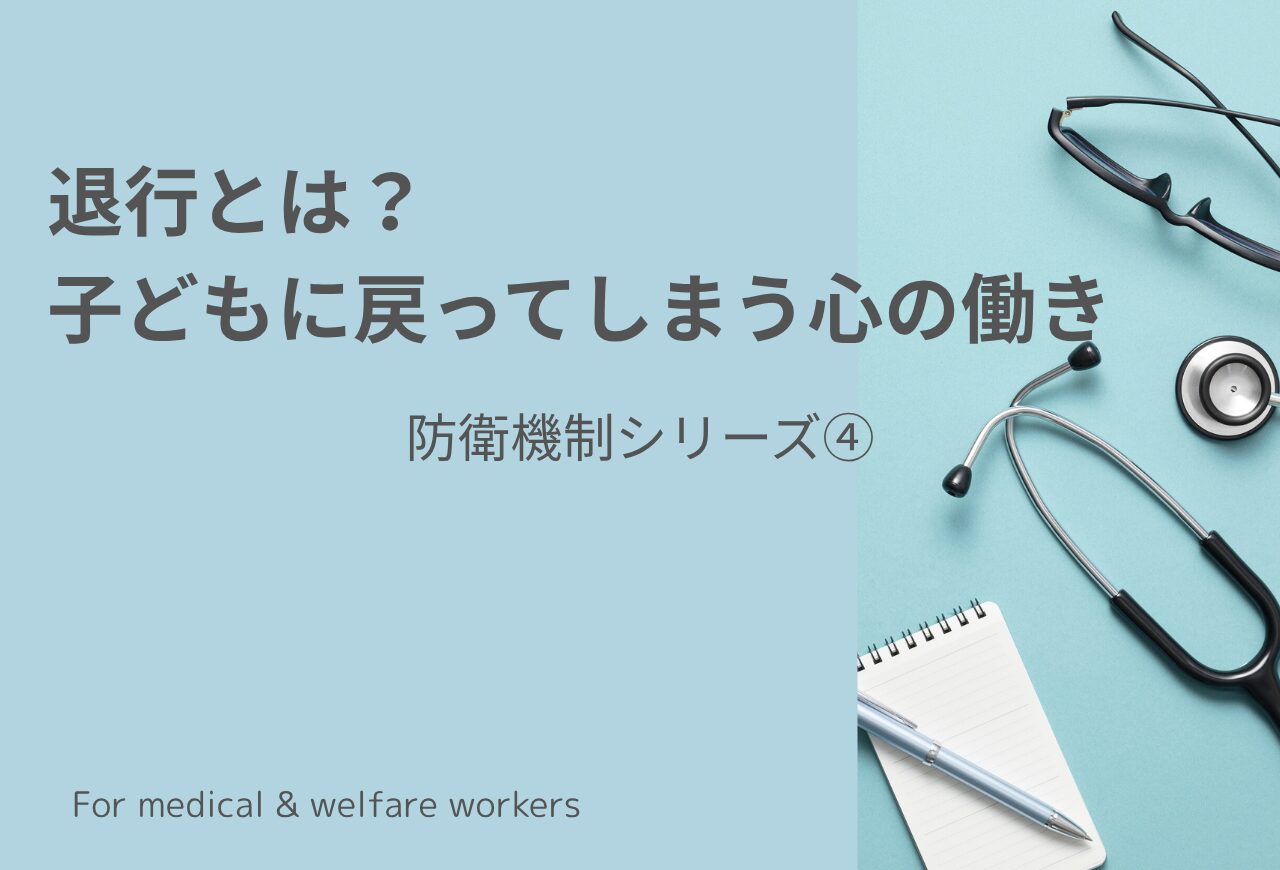
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=20480949&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F7531%2F9784479797531_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


