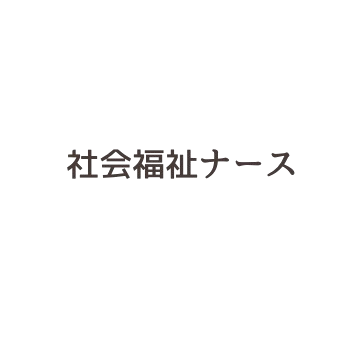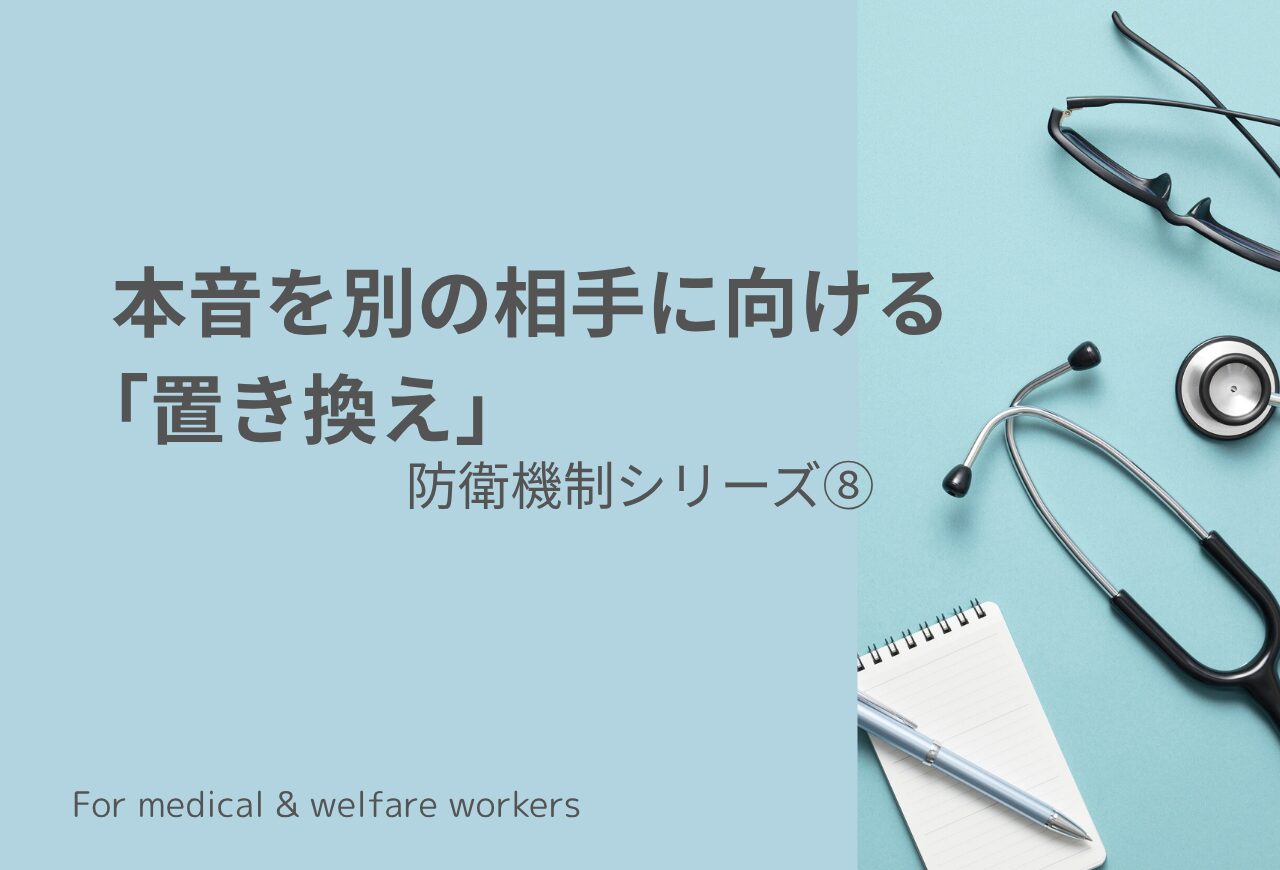人はストレスや不安を抱えたとき、その感情をそのまま表に出すことが難しい場合があります。そんなときに無意識のうちに働くのが防衛機制の「置き換え(displacement)」です。
置き換えとは?
置き換えとは、本来向けるべき相手や対象に直接感情を表現できないときに、より安全で受け入れやすい相手だと潜在的に自分が思っている相手や物にその感情を向けることです。
たとえば、上司に怒られて言い返せなかったなど、仕事でのストレスや不安がある人が、帰宅後に家族に八つ当たりしてしまうのは典型的な「置き換え」です。本人はストレスや不安があると感じていないケースも多く、家族に対してなぜかイライラする、といった感情を持つのです。
看護師の現場で見られる置き換えの事例
1. 患者対応のケース
患者さんへの不満や苛立ちを表に出せないときに、
別の患者さんに冷たい態度をとってしまう 必要以上に厳しい言葉を使ってしまう といった形で現れることがあります。
2. 看護師同士の人間関係のケース
上司や医師から厳しく指摘を受けた後、
仕事が雑になる、新人看護師など自分より立場が下の同僚にイライラして八つ当たりする、業務に直接関係のない場面で苛立ちを表す、などストレスのより多い医療現場ですので、なんとなくイメージはつきやすいと思いますし、看護師の方は想像に容易いとおもいます。
置き換えのメリットとデメリット(医療職の視点)
メリット
その場をしのげる
本来の相手に感情をぶつけることで関係が悪化するのを避けられる。
感情のはけ口になる
抑え込むよりは、感情をある程度外に出すことで心の負担を減らせる。
一時的には効果があると言えます。しかし、本当にその瞬間だけ心の負担が減るだけで、中長期的に考えると、メリットはほとんどないように感じます。むしろデメリットの方が大きいでしょう。
デメリット
関係の悪化を招く
本来とは関係のない相手に不満をぶつけることで、患者や同僚との関係を損なう。また、置き換えが繰り返されると、チームの空気が悪くなり、医療の質にも影響し、職場全体の雰囲気にも影響を及ぼしてしまいます。つまり、根本的な解決にはならない、ということです。なんなら、余計にストレスが蓄積し、かえって悪循環になってしまいます。
まとめ
置き換えは、心を守るための自然な働きですが、医療現場では患者さんや同僚との信頼関係に大きな影響を与えることがあります。
とにかく、冷静になることです。日頃から自分を客観的に見れるよう意識してみましょう。そうすることで、「本当にその人に怒りを向ける必要があるのか?」と一度立ち止まることができます。ストレスマネジメントやアンガーマネジメントの工夫や、安心して感情を表現できる場を持つことが大切です。
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~