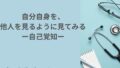🌿はじめに
「なんとなくやる気が出ない」
「小さなことで涙が出そうになる」
「疲れているはずなのに眠れない」
それは、身体ではなく“心”のほうが疲れているサインかもしれません。
私も病院で働いていた頃、心の疲れに気づく前に無理をして、体調を崩した経験があります。そして結局、体調不良から、適応障害だと診断されました。
がんばりやさんの日本人は、体調を崩す=身体の病気 だと考えがちです。
しかし、身体の病気になってしまう前に、心が病気になっていることもよくあります。そして、その心の病気がおきる前には、ちょっとした体調不良がよくみられます。
病気とまでは行かないから、大丈夫だろう、と考えるのが、がんばりやさんの日本人です。でも、それは心の病気の一歩手前の、「心の疲れ」なのです。
「病気」になってしまうと、治るのに時間がかかります。でも、「疲れ」なら、回復もはやいです。なので、「疲れ」に気づくことがとても大切です。
今日は、そんな「心の疲れ」に早く気づくための3つの方法をお伝えします。
🌸1. 身体の変化に目を向ける
心が疲れてくると、最初にサインを出すのは身体です。
朝起きたとき、胸が重たい 食欲や睡眠のリズムが乱れる 肩こりや頭痛が続く
これらは、ストレスで自律神経のバランスが崩れているサインでもあります。
ストレスを感じると身体の内側の筋肉がしらないうちに緊張します。それが胸の重たさや肩こりにつながっているのです。
それは、病気とまではいかなくても、心と体が「ちょっと休ませて」と言っている状態です。
🪷ワンポイントセルフケア
夜寝る前に“3回深呼吸”をして、1日をリセットしてみましょう。
4秒深く吸って、7秒とめて、8秒かけて大きく吐く。それだけでも副交感神経が働いて、身体が「休むモード」に切り替わります。
ストレスで凝りやすい、身体の内側の筋肉の中で、唯一、自分の意識で動かすことができるのが、呼吸にかかわる筋肉だからです。
おまけ:ストレス軽減の身体からのアプローチ方法についてもう少し詳しく知りたい人はこちらもどうぞ🌿ストレスと身体のつながりを整えるセルフケア
🌼2. 感情の変化を見逃さない
心の疲れは、感情の揺れとして現れることもあります。
いつもよりイライラしやすい 楽しいことをしても心が動かない 「何も感じない」状態が続く
看護の現場でも、こうしたサインを見逃さないことが大切でした。
感情が鈍くなるのは、心が自分を守ろうとして“感覚を閉じている”状態。
責めるのではなく、「今は守りの時期なんだな」と優しく受け止めてください。そして、休息の時間をとってください。
🪷ワンポイントセルフケア
毎晩、「今日いちばん印象に残った出来事」を1行メモしてみましょう。
うまく言葉にならなくても、「なんとなくもやもやした」だけでOK。
ことばにして自分を外側から見てみること、それが心の整理の第一歩になります。
🌷3. “いつもの自分”と比べてみる
心の疲れは、日々少しずつ積み重なるもの。
だからこそ、“いつもの自分”との違いに気づくことが大切です。
たとえば、
通勤途中の音楽がうるさく感じる 人と会うのが少し億劫になった 休みの日も「休めていない」感覚がある
こうした変化があるときは、無理に頑張らずに一度ペースを緩めるサインです。
私はその合図を感じたとき、スマホも何もかも手放して、お風呂場に向かいます。バスソルトを入れて、ゆっくりバスタイムをとることにしています。
香りや温かさが、「今ここにいる」感覚を取り戻してくれます。また身体の血の巡りをよくして、凝りもほぐしてくれます。
🫖もし気になる方は、私が愛用しているバスソルトもおすすめです。とくに、青色のグーテナハトはおだやかな香りでやきれいな深い青色につつまれ、香りからも、目からも、癒やされます。
→
🌙おわりに──気づくことから、回復が始まる
心の疲れに気づくのは、弱さではなくやさしさです。
自分をいたわることができる人ほど、長く人を支え続けることができます。
今日は、ほんの少しでいいので、
「わたしは疲れているかもしれない」と認めてみてください
それが、回復の第一歩です🌿
自分の心を知るための、「心の働き」についてやや専門的ですが記事を書いています。よければそちらものぞいてみてください。防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~
🪞あなたの「心の疲れサイン」は?
よければ、Xで教えてください🩵
→ 社会福祉ナース X http://x.com/shakai7nurse
次回の記事では、
「何もしたくない日の過ごし方」についてお話しします。「“何もしたくない日”の過ごし方──休むことに罪悪感を感じるあなたへ」
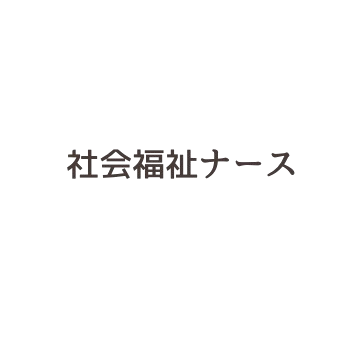

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d36b22a.772b02e8.4d36b22b.fc300a20/?me_id=1212227&item_id=10012324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkoyama-p%2Fcabinet%2Fseiatsu%2F2%2Fosukinakaori16.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)