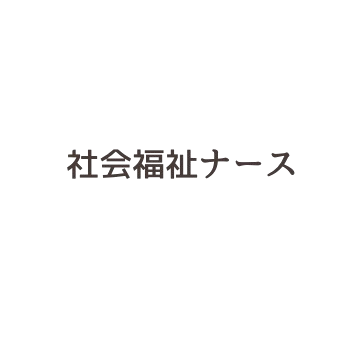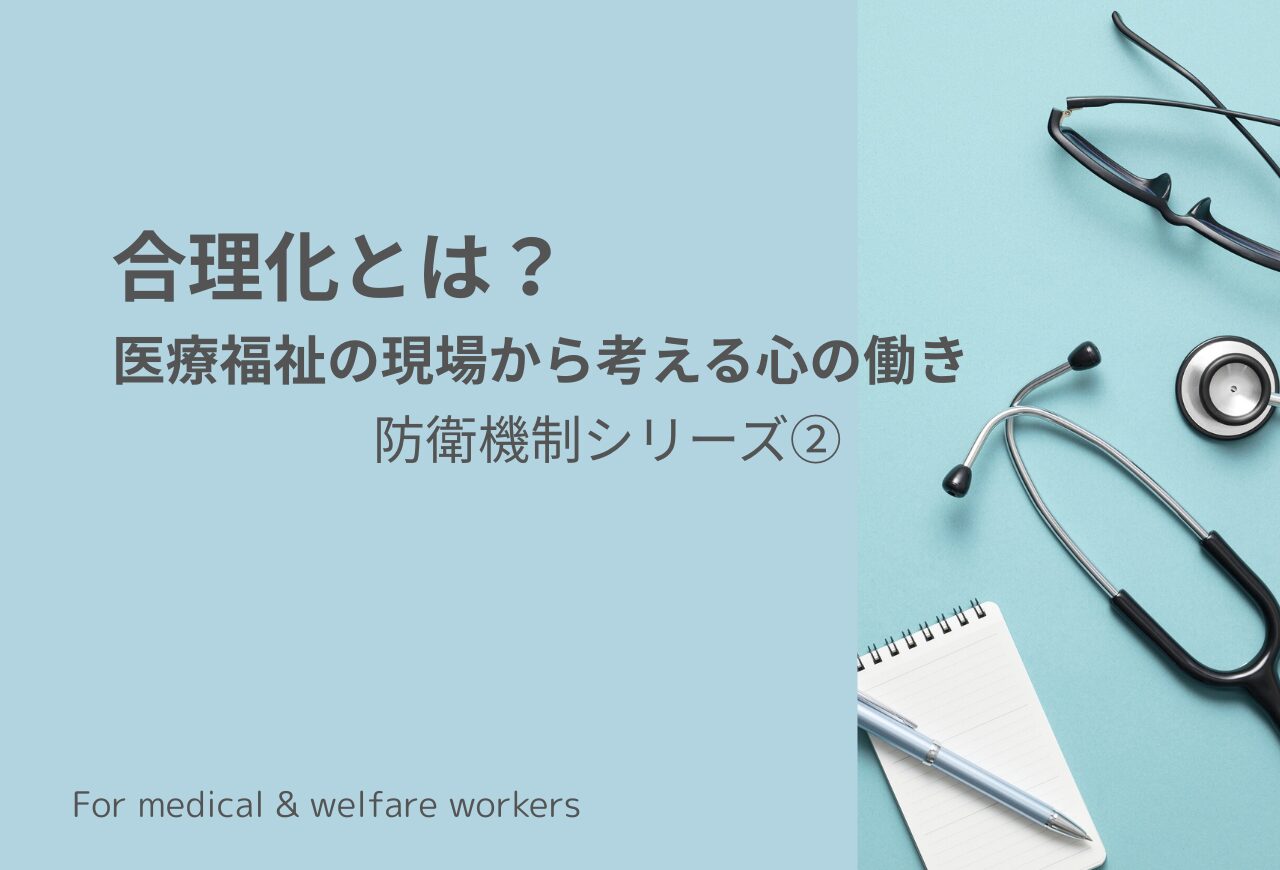以前書いた、反動形成の記事反動形成。わざと逆のことをする?バーンアウトを避けるためにに目を止めてくださる方が多く、防衛規制の話をまた書こうと思いました。この辺りの心理学、好きなんですよね。
私たちは日常の中で、知らず知らずのうちに「防衛機制」と呼ばれる心の働きを使っています。これは、ストレスや不安、葛藤から自分を守るための無意識の心理的な仕組みです。その中でも「合理化(rationalization)」は、特に多くの人が経験したことのある防衛機制です。
合理化とは?
合理化とは、自分の行動や失敗、望んだ結果を得られなかったときに、それをもっともらしい理由で説明し、納得させようとする心の動きです。要するに「言い訳」や「正当化」に近いものですが、本人にとっては本気で納得できてしまうのが特徴です。
有名なものでは、イソップ童話の「キツネと葡萄」があります。葡萄をどう頑張っても手に入れられなかったキツネは、しまいに、「どうせあの葡萄は酸っぱかったんだ」と言って終わるのでした。
看護師の現場で見られる合理化の事例
今回は、私の経験のある病棟という場でのことを挙げましたが、介護職の方でも、あるあるだと思います。
1. 患者対応のケース
病棟で忙しい中、優先度の高い患者さんからのナースコールにすぐ対応できなかったときに、
「他の患者さんの処置も結構優先度が高かった。だから仕方がない」 「ナースコールが多すぎるから、全部に対応するのは不可能」 と考えて、自分の罪悪感や無力感を和らげることがあります。
この合理化は一時的に気持ちを落ち着けますが、同時に「どうすれば呼び出しに効率よく対応できるか、どうすれば優先順位を適切につけることができるか」といった、成長につながる改善の視点が後回しになりかねない、といったデメリットにもつながります。
2. 新人や同僚との関係のケース
新人看護師がミスをしてしまったときに、先輩看護師が心の中で
「この職場は忙しすぎるから、教える暇もない、きちんと見てられない、自分の仕事で精一杯」と考えて納得する、とか、
あるいは、新人看護師が先輩から注意を受けたときに、
「あの先輩は機嫌が悪いだけ」 「本当は自分のせいじゃなくて、システムに問題がある」 と正当化することで、プライドや落ち込みから自分を守ること、あるのではないでしょうか。
こうした合理化は人間関係のストレスをやわらげますが、必要以上に繰り返すと「成長や信頼関係の構築」の妨げになってしまいます。
合理化のメリットとデメリット(医療職の視点から)
メリット
心の負担を軽減する 看護師は常に人の命や健康を預かっており、失敗やミスに大きなプレッシャーを感じます。合理化は、その重圧から一時的に自分を守り、業務を続ける力になります。バーンアウト( 燃え尽き)や、過剰に自責感を抱くことを防ぎ、気持ちを切り替えて次のケアに臨む助けとなります。
デメリット
改善の機会を逃す 合理化ばかりに頼ると、業務の工夫や安全対策に目が向きにくくなり、同じミスが繰り返される可能性があります。 チーム内の信頼低下 言い訳に聞こえてしまうと、同僚や上司から「責任を回避している」と受け取られ、信頼関係に影響を及ぼすことがあります。
反動形成と合理化
合理化は「心を守る自然な心理的働き」であり、看護師のようにストレスや責任の大きい職場ではあって然るべきです。
以前、反動形成について書きましたが、反動形成は長期的にみればバーンアウトの要因になってしまうのに対して、こちらは短期的な反応であれば、バーンアウトを防ぐ役割があるからです。ですので、合理化という防衛機制はある意味、長く仕事を楽しく続けるには必要と言えるでしょう。
しかし、言い訳で終わらせるのではなく、「なぜそうなったのか?」を振り返る時間を持つことが、専門職としての成長やチーム医療の質向上につながることもまた、事実です。
まとめ
反動形成にしても合理化にしても、一時的な反応としてうまく対応できれば素晴らしいと思います。自身の心の動きや考え方を、客観的に見るよう意識づけることで、うまく対処できているか、理解しやすくなると感じています。
他の防衛機制について
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~