防衛機制の一つである「同一化(identification)」は、他者の特徴や価値観を自分のものとして取り入れる心の働きです。単に真似をするだけでなく、自分の自信のなさや不安を和らげるために無意識に使われることもあります。
同一化とは?
同一化は、自分が弱いと感じたり不安を抱いたときに、「強い存在」「尊敬できる人」「安心できる対象」と自分を重ね合わせることで安心感や自信を得る防衛機制です。
身近な事例
子どもがヒーローに憧れて「自分も正義の味方だ」と思い込むことで安心する。 学生が、部活で憧れの先輩の言葉づかいや立ち居振る舞いを真似することで、自分の自信につなげる。など挙げられるでしょう。最近のアイドルの存在意義も、もしかしたらこのような力をファンに与えているのではないだろうかと感じたりします。
看護師の現場で見られる同一化の事例
1. 患者対応のケース
新人看護師が先輩の姿を「理想の看護師像」として強く意識し、同じような言葉遣いや態度を取る。 経験豊富な同僚を手本にすることで、不安な状況でも「自分もできる」と思える。
2. 自分自身のケース
医師や先輩に強い憧れを抱き、「自分もそうなれる」と考えることでプレッシャーを乗り越える。 著名な看護師やロールモデルの言葉を自分に重ね合わせて、困難を前向きにとらえる。
3. 看護師同士の人間関係のケース
チーム内で尊敬するリーダーに強く同一化し、考え方や態度を取り入れることで安心する。 逆に、権威のある人物に過剰に同一化しすぎて、他の人との関係に摩擦が生じる場合もある。
同一化のメリットとデメリット(医療職の視点)
メリット
学びや成長につながる
尊敬する人を真似ることは、スキルアップや専門性の獲得に直結します。 また、経験不足の場面でも「先輩ならこうする」と考えることで安心感が得られ、実際に行動に移すこともできるようになります。また、この「同一化」がうまく働けば、個人の学びや成長につながるだけでなく、個人がスキルアップしていくことで、職場全体の士気もあがり、職場全体の成長にもつながる可能性も十分にあるでしょう。
デメリット
自分らしさを失うリスク
他者に同一化しすぎると、自分自身の強みや個性を発揮しにくくなります。 常に誰かを基準にしてしまうので、その人の行動に依存的になり、自分の判断に自信が持てなくなってしまいます。それが度を過ぎると、完全に自分を見失ってしまうことになります。また、尊敬する対象が必ずしも正しい行動をとっているわけではないので、あるときそのことに気づいた瞬間から、自分の存在意義が分からなくなってしまう危険性があります。
まとめ
同一化は、憧れや尊敬を自分の力に変える心の働きであり、特に看護(看護でなくても仕事)の学びや成長の過程で大きな役割を果たします。
ただし、あまりに盲目的にその対象を信じ切ってしまうのは大変危険です。「誰かのようになりたい」という気持ちは大切ですが、憧れ程度にとどめておき、良いところや、自分にとっての改善すべき部分は参考したり真似たりして、自分自身の看護観やスタイルを育てていくほうが、より豊かな成長につながるでしょう。あの人はあの人、あなたはあなた、私は私、なのです。
他の防衛機制について
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~
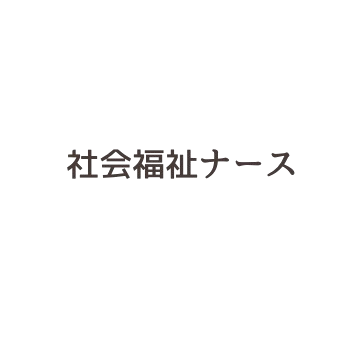
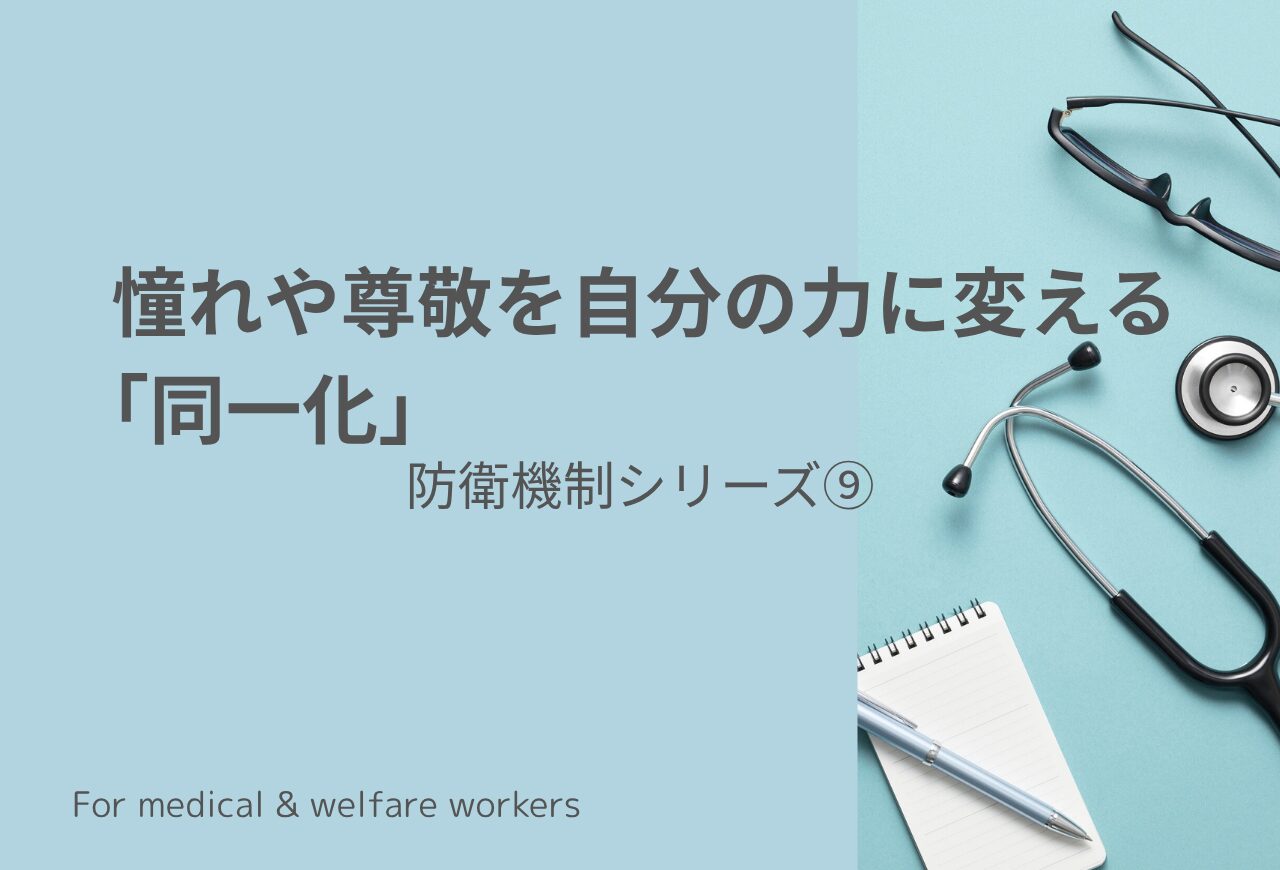
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=20480949&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F7531%2F9784479797531_3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


