社会福祉士国家試験に向けて勉強していく時に、たくさんの科目がある中で、一体どこから手をつければいいか、ズバリお伝えします。
国試勉強って、ほとんどが知識を身につけることから始まりそれに終わるという感じがします。過去問などの問題集を解きまくる方法をとっていても、どこかの時点では必ず自分の知識を再確認しなければならない時間にぶつかるのです。遠回りそうに見えて結局近道で効果的な方法が知識を入れること、知識の確認になります。(シンプルで効果のある学習方法についてはこちら→社会福祉士国家試験(これから初めて手をつける人へ。必勝法、見せます))
覚えなければならない知識も膨大にある中で、まずどこから覚えると良いのか考えるばかりで、学習が始まらなければ元も子もありません。もう結論からまず、お伝えしましょう。
戦後~現在の、日本の社会保障制度の発達過程の概要から始めてください
大切なことなので目立たせてしまいました。ここを学習の入口にすると良い理由についてお伝えしようと思います。
現代の日本社会福祉に直接繋がっている範囲だから
私たちは現在、様々な社会制度の中で生活していますが、それらができあがった過程というのが、だいたい戦後から始まっています。戦前についても最終的には覚える必要がありますが、優先順位としてはまず、戦後から現在の制度の発達について知る必要があります。それにより、今の日本社会における社会保障を知ることになるからです。
他の科目の学習がしやすくなるから
試験科目は相互に内容が重複していることが多く、例えば社会保障制度の成り立ちを学んでしまえば、地域福祉や障害者福祉、高齢者福祉など、個別の専門的な科目の制度のあらましをもう理解していることになりますので、学習を効率的に行うことができます。
他の国を学ぶ前にまず自国を知ることで比較しやすくなるから
試験に出るのはなにも日本のことだけではありません。それでも、日本の社会福祉士の資格ですから、日本を中心として試験は作られています。その上で、福祉先進国であったイギリスやアメリカの歴史は日本の福祉を語る上では避けられませんし、その他の国の社会保障について理解することは日本の社会保障の特徴を知ることにもなります。まず自国のことを理解してから、他の国を学び、それらの国から今度は日本を他覚的に見ることで学びも深まります。
つまり、単純に、ここを中心として現代の日本が成り立っている、ということは、ここを中心として問題が作られやすい、ということだからです。
しかし学び方にもコツがある
さて、戦後から現在にかけての社会保障制度の発達過程について、まず元に学ぶことをおすすめしました。しかし、ただ、作られた法律とその年号だけ覚えるのはかなり難しいです。ここでは、記憶に残りやすくする2つのポイントをお伝えします。
ストーリーを大切に
社会保障制度の発達ってつまりは、歴史です。歴史というのは必ずストーリーを伴います。このストーリーを覚えていくことです。そうすれば芋づる式に知識が身につきます。現在の法律になっているものと、その過程において重要なものが分かってきますので、そこから覚えていくことです。
ストーリーのターニングポイントを押さえる
自分の人生でもそうですが、歴史や物語には必ず「転機」が訪れます。これがストーリーのターニングポイントなのですが、社会保障制度の歴史の中での「転機」は特に重要です。その転機があってこそ、今の社会が成り立っているのですから。重要なことは試験にも出やすいので、つまりターニングポイントをまずチェックすることが試験対策においても近道になります。
以上が、今回お伝えしたかったことです。皆様の学習の一助になれれば幸いです。
それでは、ここからは、では具体的な「戦後から現在における日本の社会制度の発達過程」は何か?そしてストーリーってなんなのか?このままこのブログで知りたい方は、読み進めて頂ければと思います。有料にはなりますが、特に全く勉強を始めていない、どうすればいいか分からないという方にとっては、読む価値はあると思います。おおまかに、1980年代までを理解しておけば、後は各自での勉強がはかどると感じています。
参考書で悩んでいる方におすすめはこちらです↓
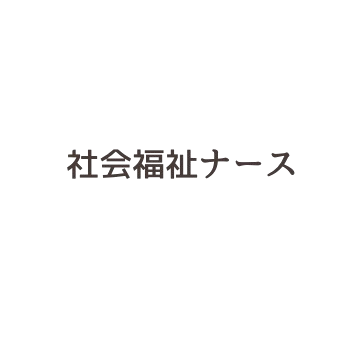
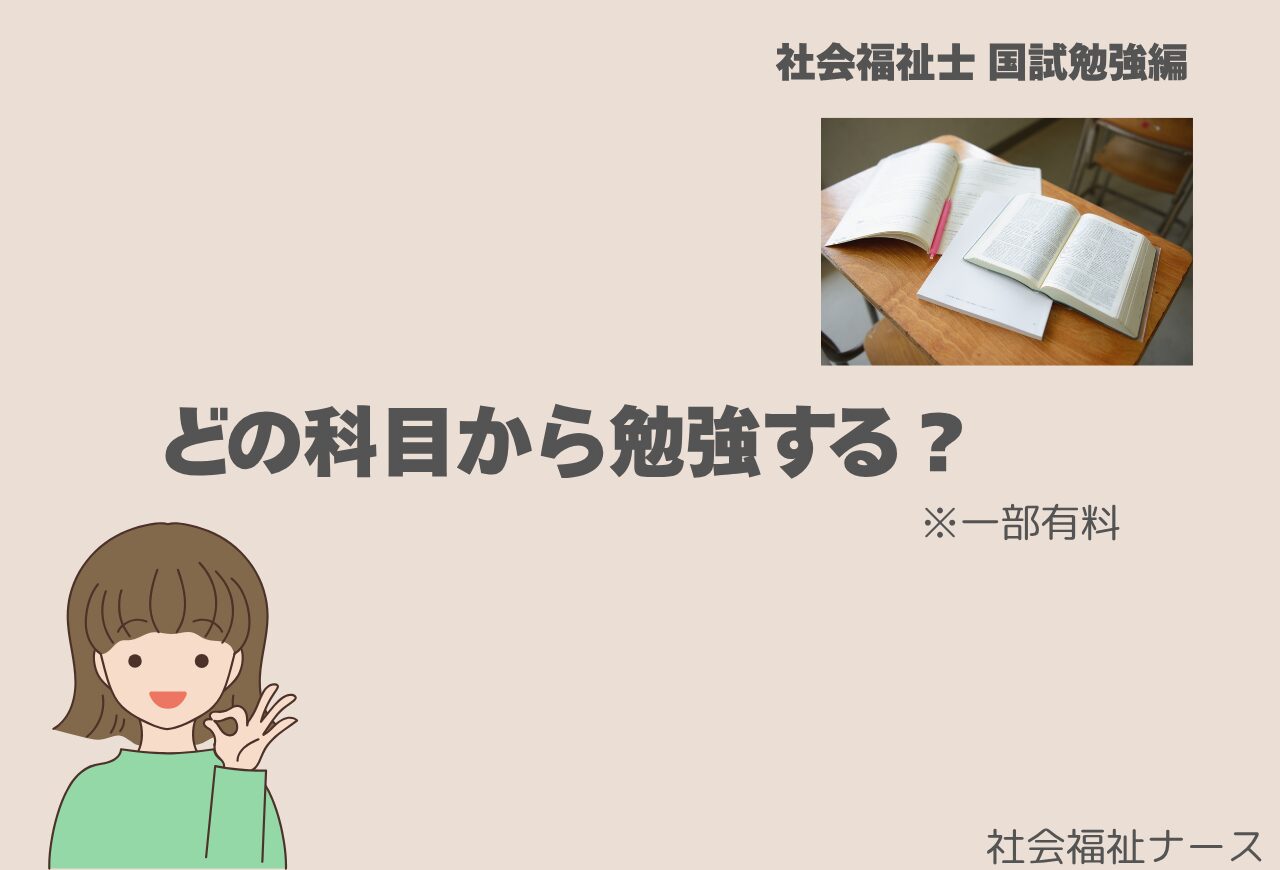
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=21567485&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9582%2F9784896329582.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント