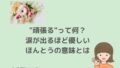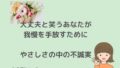社会福祉士国家試験では、「社会福祉協議会(社協)」の歴史的な背景や役割について、毎年のように出題されています。この記事では、社協の歴史を問われるポイントに絞って、サクッとまとめました。完全に試験対策用です。
■ 社会福祉協議会の成り立ち 試験に出やすい!!要チェック
福祉というのは、その性質上、富裕層や宗教関係によって支えられやすい傾向にあります。それは昔から変わらずです。←このことを知っておけば、様々な福祉の歴史が頭に入りやすくなると思います。
そして、社会福祉協議会もその一つ。そもそもその前身は、1908年に設立された中央慈善協会でした。民間のお金持ちの人たちが福祉活動にも手を出していたのですが、それを組織化することを目的としたものです。初代会長は、一万円札の顔、渋沢栄一でございます。
その後
1921年に社会事業協会に改称
戦後のGHQによる「6項目提案」等を経て
1951年 社会福祉事業法により、日本社会事業協会、同胞援護会、全日本民生委員連盟の3団体が統合され、中央社会福祉協議会となる(翌年、全国社会福祉協議会連合会へ改称。)、また、都道府県社会福祉協議会も法定化される。
↑ここで全国と都道府県での働きが本格化したと言えるでしょう。1951年は絶対覚えてください。
1953年 牧賢一「社会福祉協議会読本」
1955年 全国社会福祉協議会に改称
1962年 「社会福祉協議会基本要綱」――基本的機能は、コミュニティ・オーガニゼーションであること、住民主体の原則が明記されたこと。(つまり、住民に対して直接サービスを行うことを原則として避ける、と言うことです)
1968年 全国社会福祉協議会は民生委員と協力して「居宅ねたきり老人実態調査」を発表
1979年 「在宅福祉サービスの戦略」行政と民間団体の連携について示す。社会福祉協議会は民間の中核として位置づけられました。
1983年 社会福祉事業法改正により「市町村社会福祉協議会」が法定化。
以上が、現在の社会福祉協議会の活動に至るまでの成り立ちをピンポイントで抑えたものです。これらはすべて大事!!年号と一緒に覚えておきましょう。全国・都道府県がいつ始まったか(1951)、市町村がいつ始まったか(1983)を抑え、次に1962「社会福祉協議会基本要綱」と1979「在宅福祉サービスの戦略」の内容を抑えましょう。例えば、「住民主体の原則」ということばが出てきたら1962年の基本要綱の話になりますよね。キーワードと共に内容を理解しましょう。
ちなみに、これも大切なのですが、
都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会の過半数、及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加すること。
市町村社会福祉協議会は、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加すること。
となっています。これは過半数でなければ、その都道府県や、市町村内に2つ以上の社会福祉協議会ができてしまう、と覚えればわかりやすいでしょう。
社会福祉協議会については、覚えることはまだたくさんありますが、以外とこの歴史の部分が問われることが多いです。対策していれば必ず点になるところですので、覚えてしまいましょう。
おすすめ参考書↓この2冊で合格しました。
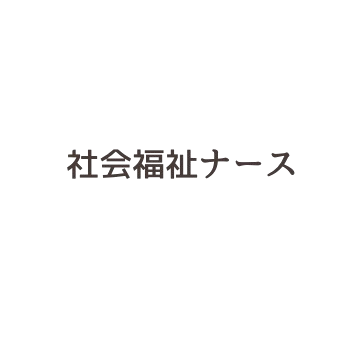
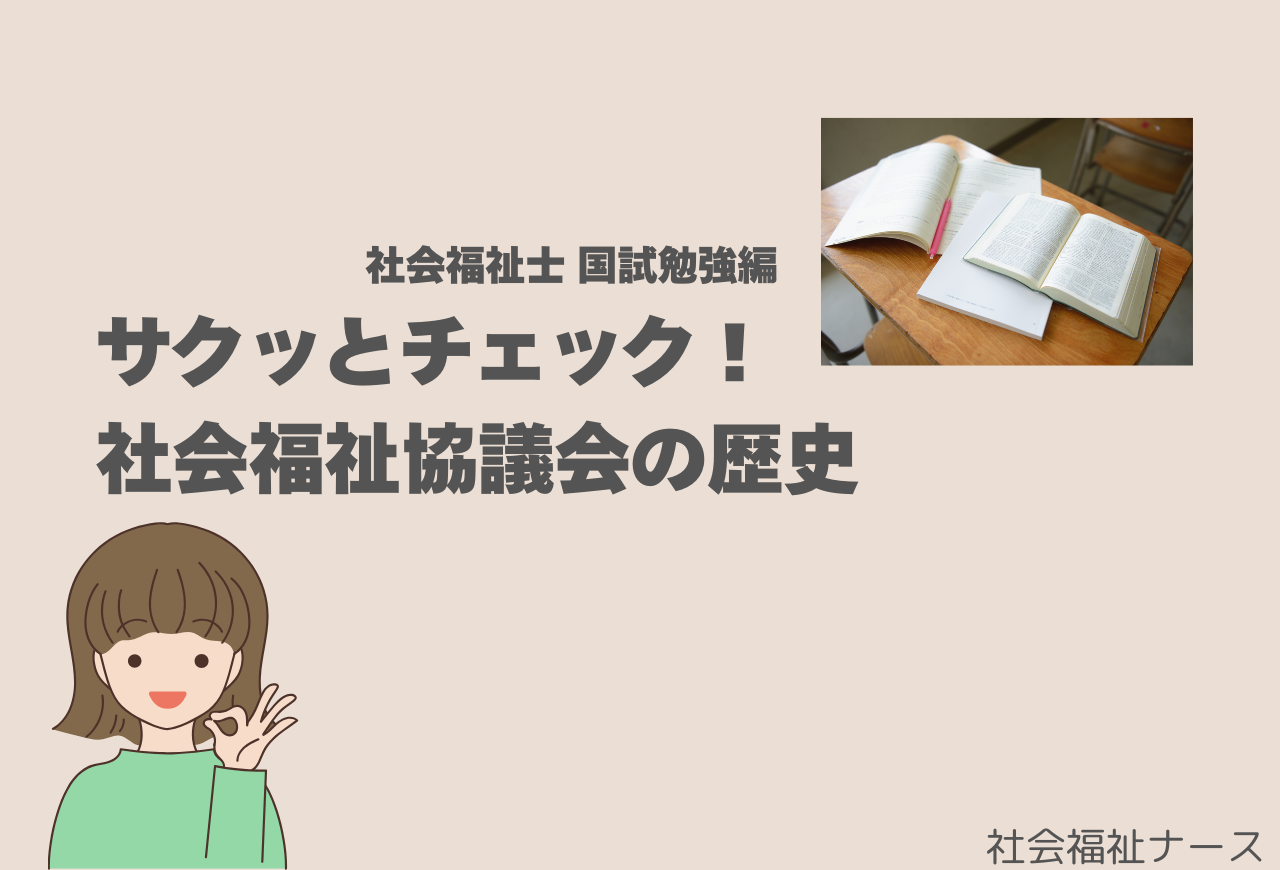
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=21567485&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9582%2F9784896329582.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d9e6ab0.3f622ca1.4d9e6ab1.8afc1d94/?me_id=1285657&item_id=13030810&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01156%2Fbk4824302153.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)