防衛機制の話もさいごになってきました。今回は、「解離(dissociation)」についての話です。解離とは、強いストレスや衝撃的な出来事に直面したとき、感情や記憶を切り離して自分を守ろうとする心の働きです。とても特殊で、軽い形から重い形まで幅があると言われています。
解離とは?
解離とは、耐えがたい現実や感情を直視できないときに、意識・記憶・感情を分離させてしまう防衛機制です。
軽い場合は「一時的に心ここにあらず」となる程度ですが、重くなると記憶が抜け落ちたり、現実感がなくなる感覚が出ることもあります。
身近な事例
大事な発表や試験の時など、過度な緊張の場面で「頭が真っ白になる」ことはないでしょうか?また、強いショックなど、 ストレスを受けたときに、その出来事の記憶が抜け落ちてしまうこともあります。
看護師の現場で見られる解離の事例
1. 患者さんのケース
大きな手術や事故の後、「手術を受けたことを覚えていない」と話す。 外傷や虐待を受けた患者さんが、その出来事をまるで他人事のように語る。解離とは、心の働きであると同時に、PTSD(心的外傷後ストレス障害)など、心理的な障害にも結びついてしまう可能性もはらんでいると言えるでしょう。
2. 看護師自身のケース
緊急事態で頭が真っ白になり、普段できる処置が一瞬思い出せなくなる。 強いストレスを受けた日の勤務を「細かく覚えていない」と感じる。など、私自身も新人のころ、失敗を何度もしました。インシデントレポートという、再発防止のためのレポートを書くのですが、あまりに失敗したことがショックだったのか、詳細を振り返ろうとしても全然思い出せなく、周りの職員の方々に思い出してもらうこともありました。特に看護の現場は、命に直結するので、無意識のうちにストレスを抱えている看護師がよくいたように思います。
また、看護師が、患者さんや上司に怒られ、意識が遠のくとか、心がここにあらずの状態になることも時々見かけました。
解離のメリットとデメリット(医療職の視点)
メリット
心を守るための一時的な避難
強すぎるストレスから意識を切り離すことで、精神が崩壊するのを防ぎ、 緊急時に感情を抑え、遮断することで、その瞬間は冷静に行動できるという利点があります。
デメリット
長期にわたると悪影響が
解離が強く起こると、記憶や集中力に支障を来し、必要な判断ができなくなってしまいます。したがって、看護師であれば、ケアの質や、患者さんへの対応に影響することがあるでしょう。また、 トラウマや強いストレスの根本的解決ができていない状態なので、心身の不調につながる可能性があります。
まとめ
解離は、強いストレスから自分を守るための特殊な防衛機制です。
一時的には心を保つ助けになります。しかし、解離が繰り返されると、記憶や判断力、そしてケアの質に影響を及ぼす可能性があります。こまめに、自分の心を見つめるように意識しましょう。
ここまで、防衛機制について書いてきましたが、伝えたいことは、自分の心や考えを意識的に見つめ直す、ということです。自分の気持ちは大事にしつつも、このような知識を知ることで、自分の外側から自分自身を客観的に見つめることができるようになれば感情のコントロールもできるようになります。特に、医療福祉に携わる人たちは、対人関係を基本にした仕事になります。人と関わる際に、まず自分がどのような人間なのか知っておくことは大切です。これを「自己覚知」と言います。このことについて次回、まとめていきます。
ちなみにこれらの防衛機制については、看護師国試にも、社会福祉士国試にも出題される可能性は十分あります。その点でも覚えておいて損はないでしょう。
他の防衛機制について
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~
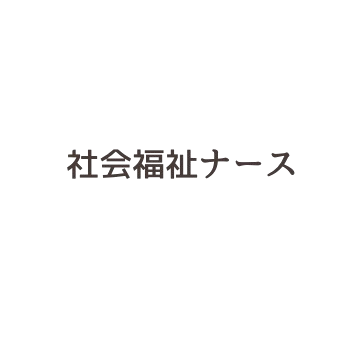
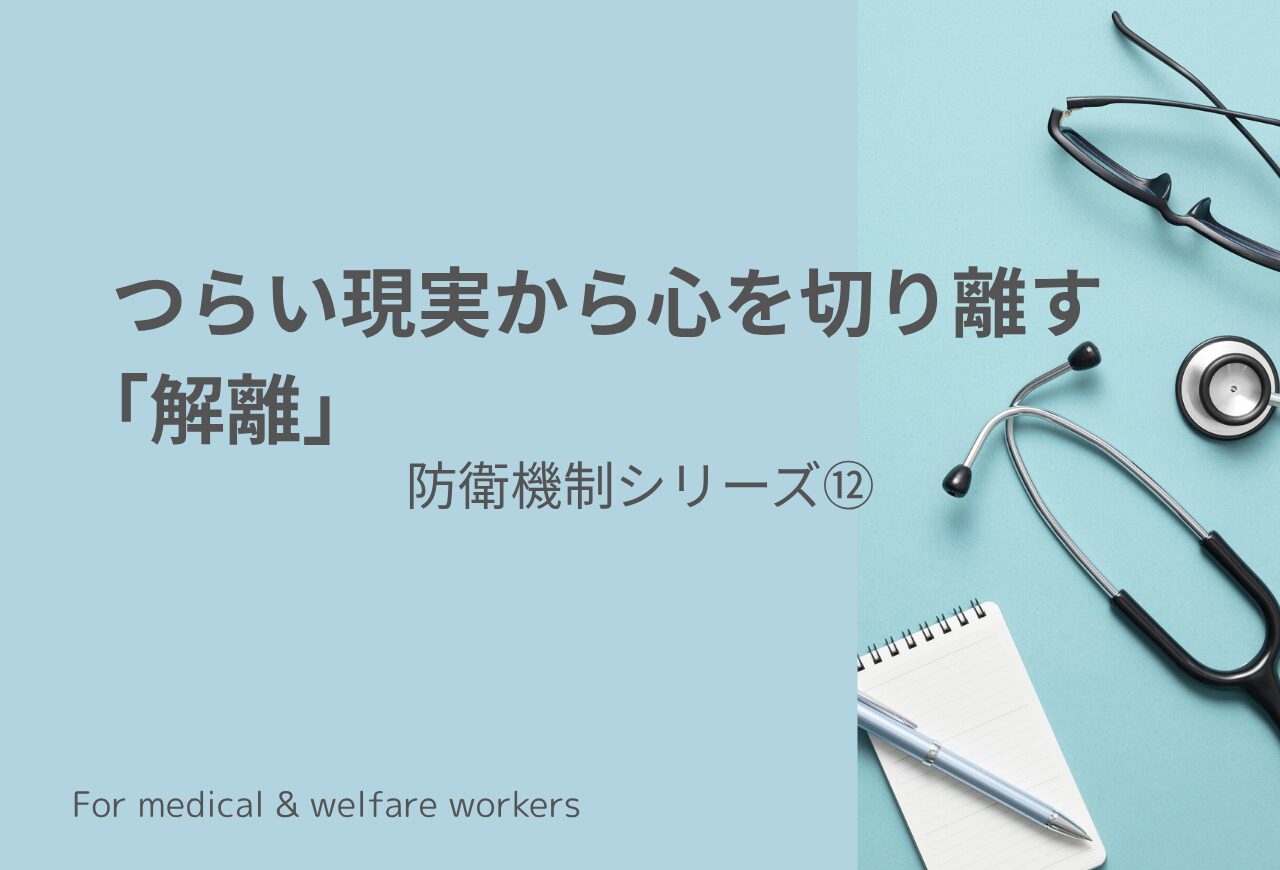
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=20480949&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7531%2F9784479797531_1_3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


