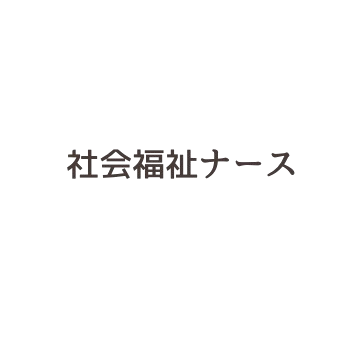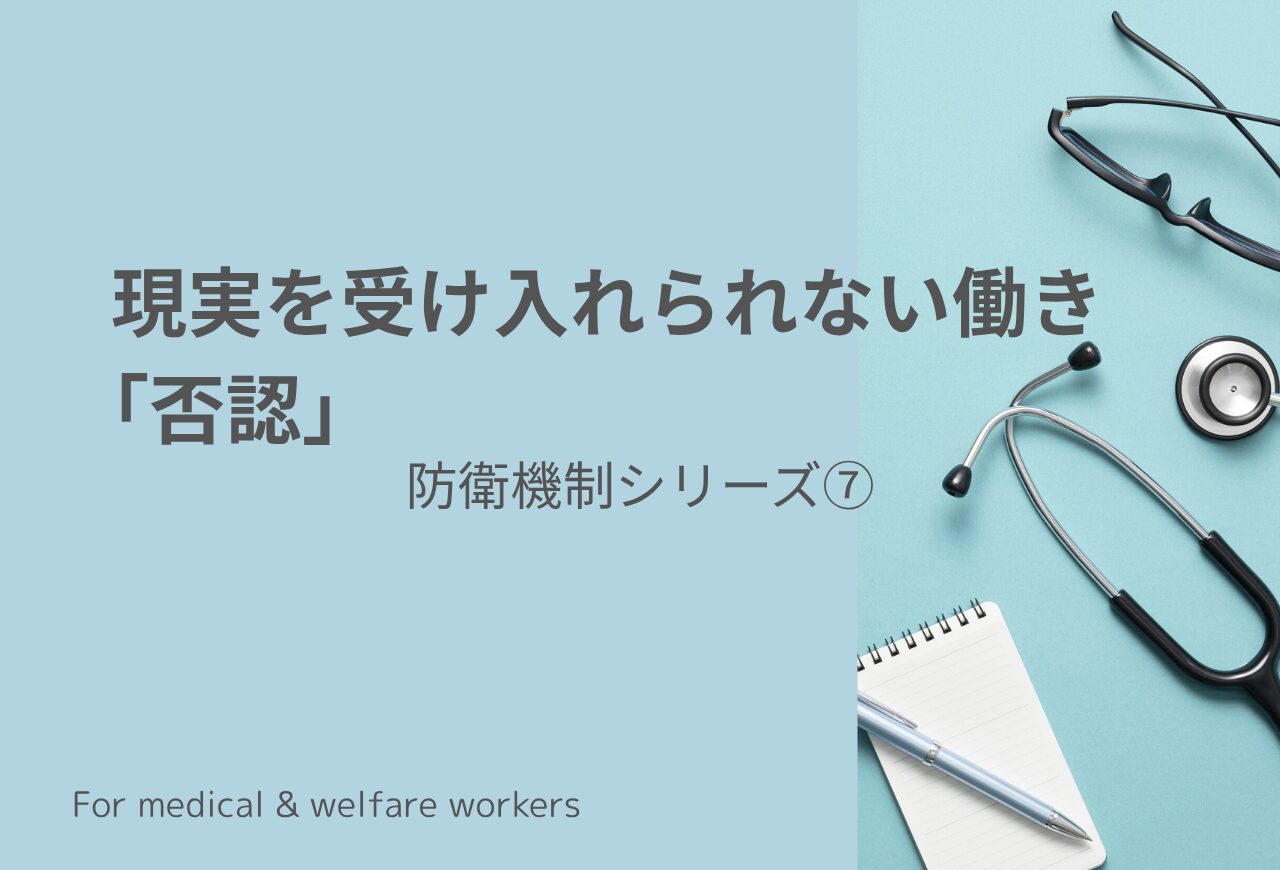防衛機制の一つである「否認(denial)」は、受け入れがたい現実を「存在しないこと」にしてしまう心の働きです。とても強力な防衛機制であり、医療現場でもよく見られる反応の一つです。
否認とは?
否認とは、つらい出来事や不安を引き起こす事実を認めずに「そんなことはない」「起きていない」と感じてしまう無意識の反応です。一時的には心を守りますが、現実に向き合うことを遅らせることにもつながります。
キューブラー・ロスの「死の受容過程」はご存知でしょうか?これは、看護理論でもあるのですが、死に直面した患者が、自分の死をどのように受け入れていくか、5段階で分けています。その中で初めにまず多い反応が、「否認」です。そんなはずはない、と感じるのです。例えば、自分のことを考えてみても、今日突然、余命を宣告されたら、嘘だあーと思ってしまうのではないでしょうか?
ちなみに、この「死の受容過程」の5つの段階は、
否認→怒り→取引→抑うつ→受容
です。必ずしもこの順番になることもありませんし、必ず全てを経験する分けでもありません。また、→を行ったり来たりすることもあります
身近な事例
日常生活の例
恋人に別れを告げられても「きっと冗談だ」と思い込む。 健康診断で異常を指摘されても「自分は大丈夫だ」と信じ、再検査を避ける。
看護の現場で見られる否認の事例
1. 患者さんのケース
重い病気の診断を受けた患者さんが「間違いだ」と信じて治療を拒む。 余命宣告を受けても「そんなはずはない」と受け入れられない。
先ほどの「死の受容過程」で挙げたとおりです。
2. ご家族のケース
患者さんの病状が悪化しているにもかかわらず、「きっと元気になる」と言い続ける。 看取りの段階に入っても「まだ治療すれば助かる」と信じ続ける。
3. 看護師自身のケース
心身の疲れを感じても「まだ大丈夫」と思い込み、休養をとらない。 ミスや限界を受け入れられず「自分は問題なくできている」と考えてしまう。私に限って精神を病むことはない、と思って自分をだましたまま仕事を続け、バーンアウトすることもあります。
否認のメリットとデメリット
メリット
心を守る一時的な盾になる
すぐに受け入れるのが難しい現実から自分を守り、心が崩れるのを防ぐ効果があります。実際、その信じられない出来事が本当でなかった場合や、それほど深刻な問題でなかった場合には、精神的な大きなダメージを受けることなく過ごせることができるでしょう。
時間を稼げる
感情を整理するまでの間、冷静さを取り戻す準備ができます。受け入れるまでの間に、必要な過程でもあります。
デメリット
治療や対応が遅れる
否認が長引くと、病気や問題への適切な対処が遅れてしまう。
人間関係のすれ違い
医療者と患者・家族の間で認識のギャップが広がり、信頼関係に影響を与える。
自己ケアの妨げになる
看護師自身が否認を続けると、燃え尽きや心身の不調を招く可能性がある。
まとめ
否認は、防衛機制の中でもとても基本的で、誰にでも起こり得る心の働きです。
医療現場では、患者さんや家族の「否認」に出会うことは少なくありません。その際は、無理に現実を突きつけるのではなく、その人が少しずつ受け入れられるように寄り添うことが大切です。看護師自身においても、信じられない、と思ったその気持ちは、まず大事にしましょう。
なかなかこの場合は、冷静になって「自分が否認しているかもしれない」と客観的に見ることはできないでしょうし、否認していると理解したところで、その否認の気持ち自体を無視してしまっては「抑圧」に繋がります。その気持ちを持つことはむしろ正常な反応です。ただ、あまりに長引き、建設的に物事を考えられない場合もあります。その気持ちを誰かに伝える、一人で抱え込まないことが大切です。
看護師は、自分を客観的に理解することがとても重要です。自分の気持ちについてだけでなく、知識や技術がどの程度身についているか、など、常に理解を深めていくことが大切です。最近は、オンラインなどでも気軽に学べる場が増えています。必要な時には積極的に活用するのも一つの方法です。
他の防衛機制について
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~