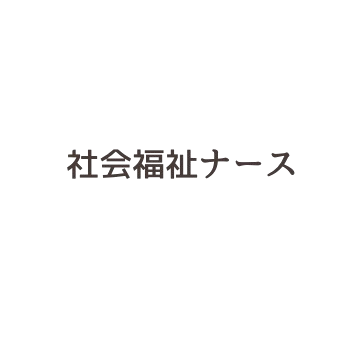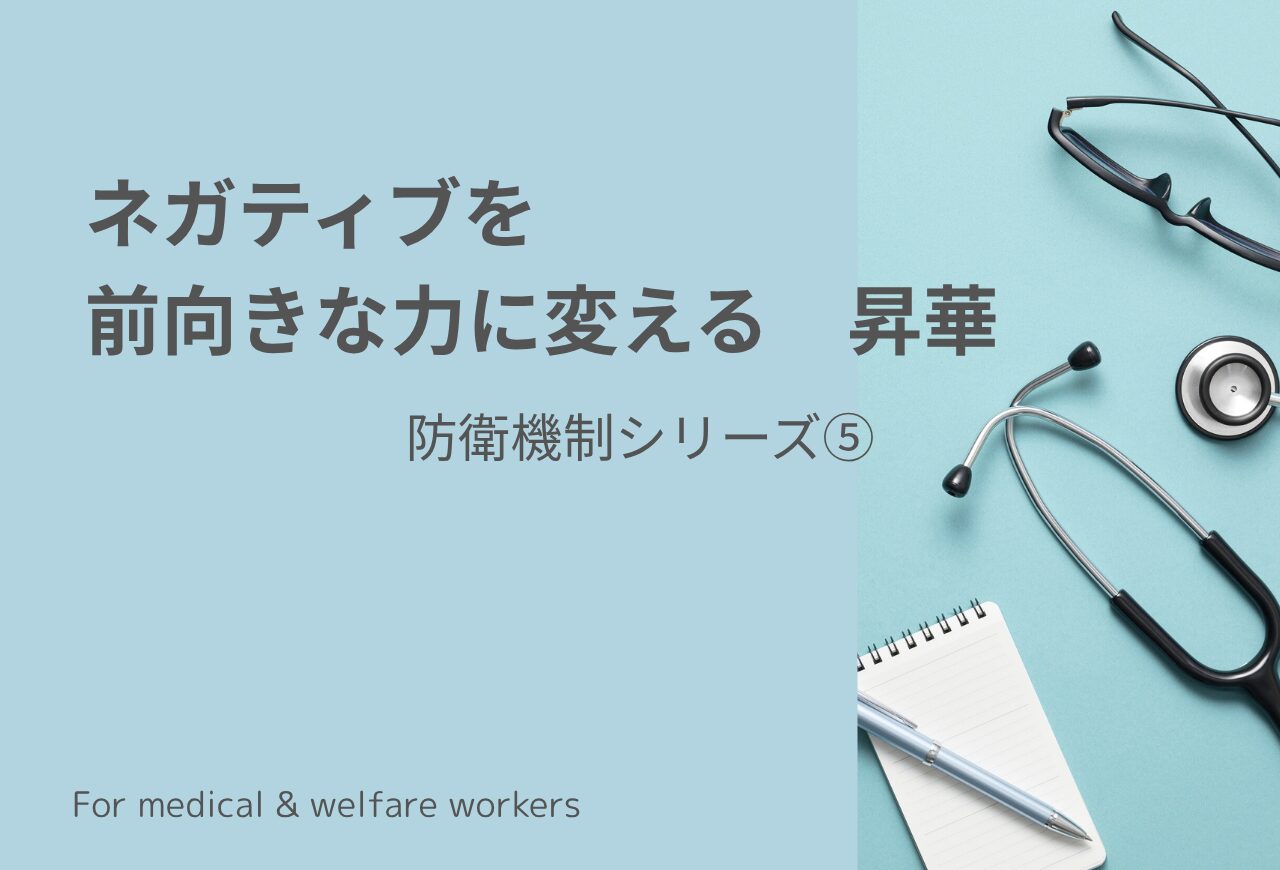人は不安や葛藤を抱えたとき、無意識に自分を守るための防衛機制を使います。その中でも「昇華(sublimation)」は、比較的健全で建設的な防衛機制として知られています。
昇華とは?
昇華とは、本来なら社会的に受け入れられにくい欲求や衝動、ネガティブな感情を、文化的・社会的に価値のある行動へと変える心理的な働きです。
たとえば、怒りや不安をそのままぶつけるのではなく、スポーツ・芸術・学び・仕事などに昇華させることで、自分自身を成長させるきっかけになります。
身近な事例
日常生活の例
ストレスがたまったときに、運動や楽器演奏に打ち込む。脳の別分野を使うので、嫌なことを忘れられた、と言った経験を持つ人は多いのではないでしょうか。私自身も、仕事で嫌なことがあっても、バイオリンを弾くと忘れられたりします。なので、これは納得です。また、一時的なことではなく、続けていくことで、文化的、学術的に大きな成果を残す人もいますよね。
学生の例
恋愛がうまくいかない寂しさを、勉強や部活動に集中することで乗り越える。昇華の事例のテッパンネタですが、とてもわかりやすいですね。何事も真剣に取り組んでいる人はやはり、ウジウジしているより遥かに魅力的です。
看護師の現場で見られる昇華の事例
患者対応のケース
患者さんとの関わりの中で感じた無力感や怒りを、そのまま態度に出すのではなく、
「もっと勉強して次はより良いケアをしよう」と学びにつなげる 「この経験を活かして後輩に伝えよう」と教育の場に生かす といった形で昇華できることがあります。
自分自身のケース
忙しい業務のストレスを、休みの日にボランティア活動や趣味に向けて、自身の経験値を高めることができます。
患者さんの死を経験した悲しみを、「より良い看取りを提供できる看護師になろう」というモチベーションに変えることも昇華に繋がるでしょう。
私自身が、看護師をしながら福祉の現場で悩んだことを、社会福祉士を勉強することで知識をつけられた。これもまた、昇華になり得るのかな、と感じました。
看護師同士の人間関係のケース
人間関係の摩擦で抱いた怒りや不満を、
チーム運営の改善提案に変える、コミュニケーションスキルの学びに活かす、といった形で昇華することもあります。昇華を個人のもので終わらせずに、周りも巻き込み言い影響を及ぼしたり、また職場の士気が良い方向にあがることもありますよね。
昇華のメリットとデメリット(医療職の視点)
メリット
感情を前向きに活かせる
ネガティブな気持ちを、そのままではなく成長や学びに変えることができます。また、バーンアウト(燃え尽き)の予防になりえます。
つらい経験を「意味あること」と捉え直すことで、看護師としてのモチベーションを維持できます。チーム全体に良い影響を与えるため、個人の努力や工夫が、周囲にも波及しやすいのです。
デメリット
気づかないうちに無理をすることがある
昇華を繰り返すことで「常に頑張らなければ」と思い込み、心身の疲労に気づきにくくなる場合があります。
感情に直接向き合う機会を失うことも
ポジティブに変換し続けることで、本来の悲しみや怒りを十分に感じる機会を避けてしまうこともあるでしょう。
バーンアウトを避けるというメリットもありますが、そのネガティブなエネルギーを、心からのポジティブな気持ちで上位のものに昇華できなければ、逆効果となり、バーンアウトの原因にもなります。この場合、もはや「昇華」ではなく、過去の記事にある「反動形成」や「合理化」に近いものとなっていると考えられます。
昇華とはそもそも、ネガティブなエネルギーを、それと同等の完全に同等のポジティブなエネルギーに置き換えるものだからです。
まとめ
昇華は、防衛機制の中でも最も建設的な形のひとつであり、看護師のように強いストレスや感情を抱く職業にとって、大きな助けとなります。
ただし、「無理にポジティブに変えよう」と頑張りすぎず、まずは自分の感情を認めた上で昇華できると、より健全な形で成長ややりがいにつなげることができます。
社会福祉ナースの思い(自分を客観的に見る大切さ)
ここまで、いくつかの防衛機制について記事を書いてきました。私自身、過去には自分のその瞬間の気持ちを一番に優先したため、全く客観的に自分の考えを分析できない時期が長くありました。そのため、仕事でバーンアウトし、その当時は、家族や職場の人全員が敵のように感じていました。そのあとしばらく休養した後、自分を正しく客観的に見つめることが大切だと知ることができました。これを、自己覚知、と言います。心理学に興味が持てたのもこのあたりからです。特に、アドラー心理学は本当に心の支えになりました。また自己覚知や、アドラー心理学についても今後、記事を作っていこうと思っています。
【日本統合医学協会】アドラー心理学検定1級講座他の防衛機制について
他の11個の防衛機制についてもそれぞれ記事にしています。コチラから→防衛機制まとめ ~心を守るしくみを理解する~