社会人として働きながら、社会福祉士の国家試験に向けて勉強されている方々も多くいらっしゃると思います。
私自身、看護師として働きながら、通信の専門学校を卒業し、国試の勉強は孤独に1人でおこないました。専門学校のスクーリングでは、先生から、学生さんは勉強する時間があるから数ヶ月前からの勉強でも間に合うが、社会人には時間がないからはやめに国試に向けて勉強に取り掛かると良い、と助言を受けたこともあります。
それだけ、勉強することにおいては、学生の方が有利な状況に置かれていると言えるでしょう。しかし、本当に学生の方が有利なのでしょうか?それが、一概にそうとも言えないのです。自身の勉強を振り返って、社会人でよかったと思えることがいくつかありました。それをお伝えし、勉強のモチベーションに繋げていただければと思います。
すでに自分の専門分野がある場合がある
例えば、私のことで言うと、看護師として働いているため、基本的な医学知識は身についています。そのため、意識的に医学概論のインプットの勉強はする必要がなく、過去問や問題集を解くのみで終わりました。当日の試験結果では6問中全問正解することができています。→第37回社会福祉士国試の振り返り
また、すでに福祉の現場で働いている方も多いと思います。例えば制度を学ぶにしても、そのような方々は、参考書で勉強するよりも、実際その制度の中で仕事されていることも多いのではないでしょうか。そのような場合、参考書での知識がすぐにイメージできたり、そもそも参考書で学ばずともその制度自体すでによく知っている、ということもあるかも知れません。
過去に学んだ分野がある場合がある
過去に大学などで学んだことのある分野が出てくることも考えられます。私の場合は、大学の際、心理学の単位を取っていたので、今回の国試の勉強の際は、こんなこと、昔勉強したなあ、と思い出しながら行っていました。
0から知識を覚えるよりは当然、楽に勉強できました。
社会保障制度には嫌でもすでになじみがあったりする
働いて雇用されている身であれば、年金制度や雇用保険などの社会保障制度は、嫌でも関わっていかなければならない基本的な制度です。
覚えることが多く確かにこんがらがりますが、自分がすでに関わっているのも事実です。ただ知識として文字や数字を覚えるのではなく、自分の身に関わっているものとして認識することで、より知識としても記憶に残りやすくなるでしょう。
社会人には、日常の中に学習のヒントがある
社会福祉士の国試の勉強内容は、幅広く、知識として覚えなければならないものもたくさんあります。しかしその一方で、時事的なもの、現代において話題となっているトピックが出題されます。新しい制度や法律、最近の社会問題、そのようなものに敏感になる必要があります。それは、参考書だけでカバーできるものではありません。日頃からニュースに触れる、市役所に行く用事があったら、そこに出ているパンフレットを見てみる、など、日常の中に勉強できる要素はたくさんあることに気づきました。
まとめ
以上のように、社会人は、いろいろな場面で社会福祉と関わりを持って生活しています。それらを意識してみる、ということが大事です。今まで気にも留めたことがないニュースが気になるようになったり、職場の中で起こったことが、社会福祉に密接に関わっていたことに気づいたりすることでしょう。
参考書での勉強は必要です。しかしそれ以外の日常の社会福祉に気がつき、それを参考書で確認するという作業が、実はエピソード記憶として頭に残りやすく、効率よく暗記できるのではないでしょうか。日頃からアンテナを張る、ということが大切で、社会人だからこそ、アンテナを張りやすい、という点をお伝えしたいと思います。
参考書で悩んでいる方への社会福祉ナースおすすめはコチラ↓
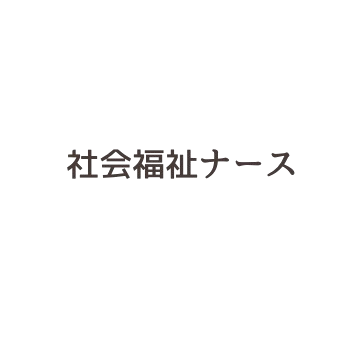
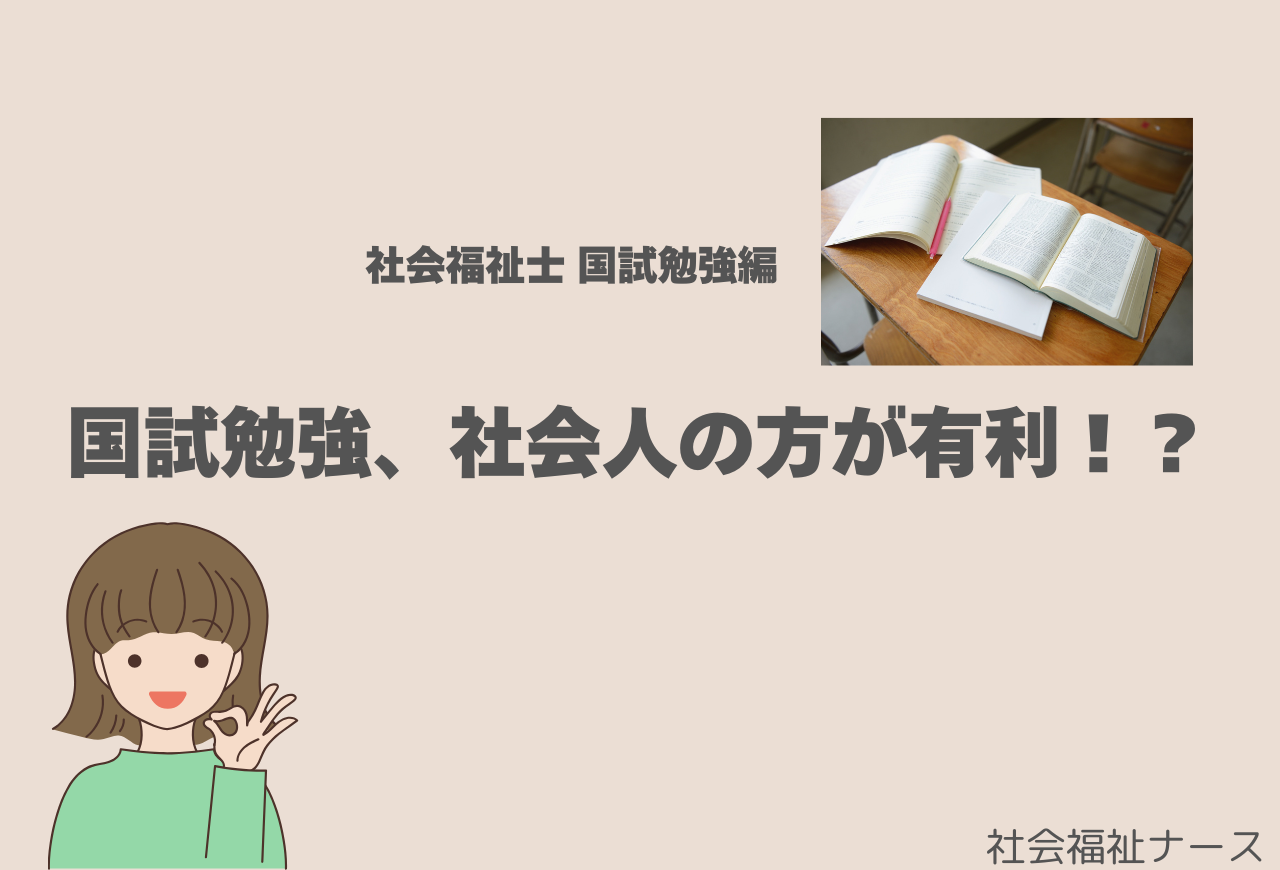
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=21567485&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9582%2F9784896329582.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


